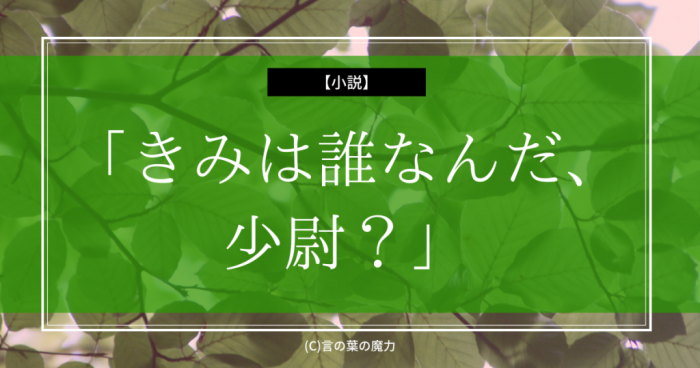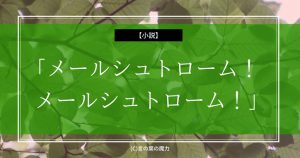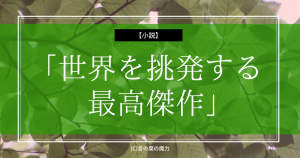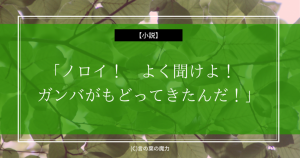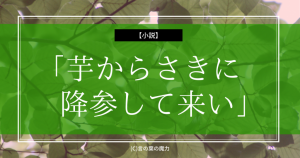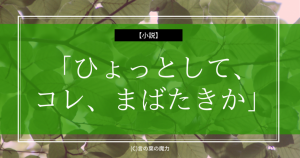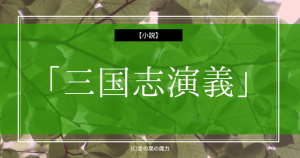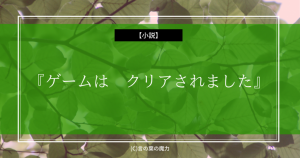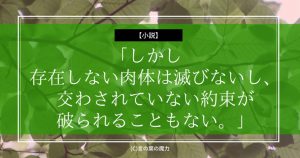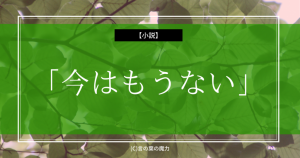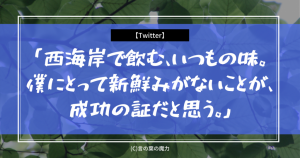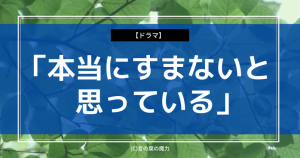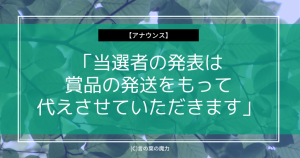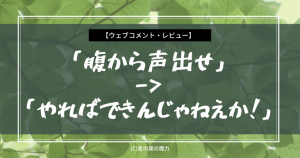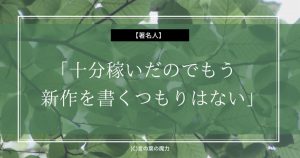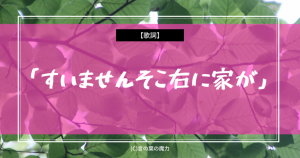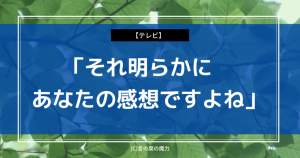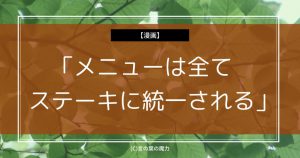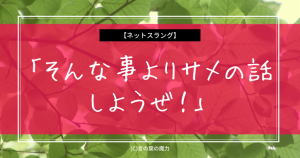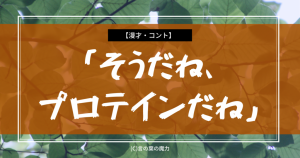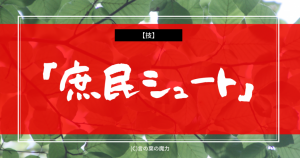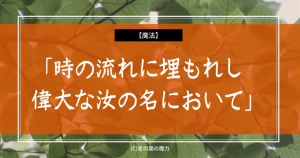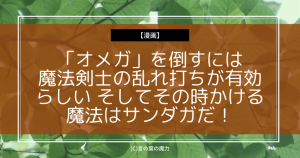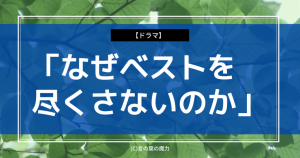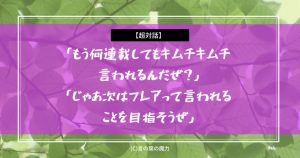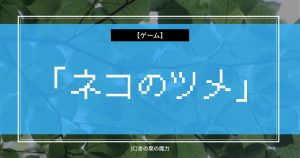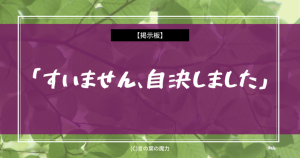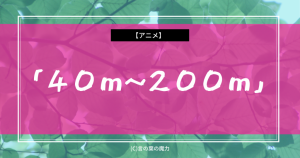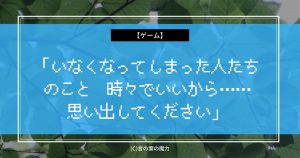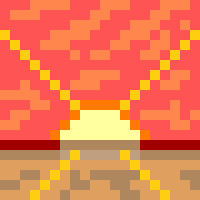「きみは誰なんだ、少尉?」
出典元、ボブ・ラングレーの小説「北壁の死闘」より。ヴァルター・ラッサー博士のセリフ。
「北壁の死闘」は名作である。山岳小説と言えば、と聞けば大抵名前が出てくるぐらいには有名な作品である。舞台はアイガー北壁。名前を聞くだけで反応する人も多いであろう、世界的に有名な難所である。
ストーリー的にはただの登山ではない。戦争物、とまではいかないが軍事活動の中での登山、いや、登攀行動だった。主人公のエーリッヒ・シュペングラーは名の知れたクライマーで、ある目的によりラッサー博士を誘拐して逃げ切らなければならなかった。しかし追っ手も迫っている。裏をかいて逃げるには、
アイガー北壁を登るしかない。
仲間もいて皆クライマーだが、博士は研究者なのでとにかく補助してあげながら登らなくてはならない。とんでもない難所をだ。しかし博士も意外と頑張れる。研究者なのに意外な頑張りに不思議に思いつつも、誘拐されながらも難所を一緒に進んで行く奇妙な一行となった。休憩中、博士がシュペングラーに聞く。
「きみは誰なんだ、少尉?」
初めは真面目に答えないシュペングラーだが、博士の質問は誘拐犯の名前を聞きたいという意味ではなかった。
「普通の男じゃ、きょうきみが登ったようには登れないはずだ」
「肉体的にとうてい不可能なピッチをきみが次々と登っていくのを、わたしはこの目で見た。きみは誰だ?」
つまり、博士はシュペングラーの事を、クライマーとして何者なのかと聞いていたのである。この二度目の「きみは誰だ?」には熱いものがある。そしてシュペングラーは正直に名前を答え、博士はクライマーとしてのシュペングラーを知っていた。博士も昔はクライマーだったのだ。ここで、博士がなかなか頑張れていた謎が解ける。博士にとって、登ること自体は初めての経験ではなかったのだ。完全に打ち解けるとまでは行かないが、多少は一体感を増し、しかし絶望的な登攀は続くのである。
ここでの一連のやり取りはとても印象深いものだったが、ストーリーもその後とんでもなく佳境を迎える。詳しくは書かないが「死闘」は敵との戦闘以外にも明らかにアイガー北壁との死闘も含まれている。最後には味方の救出を敵に求める場面もあり、一度とはいえそれに応えてくれ、クライマー同士の同族意識や自己犠牲の精神にも熱くさせられる。クライマックスの最後も最高だし、終わり方も最高である。心に残る名作である。